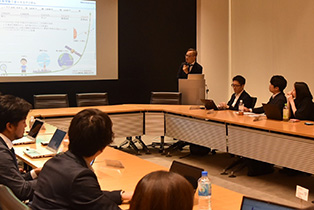活動報告(第九期)
- REPORT

第五回6月11日
テーマ
不動産市場における10年の構造変化~変化をいかにビジネスチャンスにするか~
講師榎本 英二野村不動産ホールディングス株式会社 参与
第五回目は、榎本先生による講義「不動産市場における10年の構造変化 ~変化をいかにビジネスチャンスにするか~」が行われました。講義では、最初にビジネスを考える上で将来の構造変化を見据えて「仮説」を持つことが重要であるとの話から始まりました。次に、「時代の終わりの始まり、不都合な真実が現実に?」をテーマに、「新築からセカンダリー(既存)」「世界の運用資産“2京円”の世界に向けて」「人生100年時代」「グリーン投資、新エネルギー、そしてAI/データセンターの世界へ」など9つ項目について解説を行った後、ご自身の仮説を述べられました。最後に、塾生一人ひとりが考える仮説に対して、榎本さんがコメントを添えて講義が終わりました。
【塾生の声】
今回の講義で「不動産は、流動性がある限りはマーケットの中で上がり下がりがあってもどうにかなる」というお話がありました。日頃の業務においてはどうしても近視眼的な出口戦略に陥りがちなこともありますが、不動産投資・開発は長いタームで行われる事業であり、マクロ経済、技術革新、世界情勢、人々のマインドの変化等様々な要因を踏まえて自分なりに仮説を立てたうえで考えていく必要があると強く感じました。(30代・デベロッパー)
今回講義を要約すると「10年後の未来に自身の仮説をもって事業に取り組む」になるが、多角的な視野・知見を持ち、時には大胆かつ無謀とも思われるポジティブな仮説をもつことで初めてビジネス機会が見い出せると感じた。企業に所属する中で仮説に基づく事業立案をすることは容易ではないが、企業・個人として変革が求められる今の時代だからこそ、このマインドを忘れずにチャレンジングなビジョンを持ち続けるべきと感じた講義であった。講義終盤の塾生が考える未来の仮説発表も様々な視点があり、興味深い内容であった。(30代・不動産業)

1985年慶應義塾大学経済学部卒業。1985年野村不動産入社、経理・総合企画・商品開発・資産運用事業に携わる。2008年執行役員 資産運用カンパニー副カンパニー長兼運用企画部長、2009年野村不動産投資顧問副社長、2013年野村不動産常務執行役員法人営業本部副本部長、2015年野村不動産アーバンネット専務執行役員を経て2017年同代表取締役兼副社長執行役員就任、2021年 野村不動産ソリューションズ(旧 野村不動産アーバンネット) 代表取締役副社長、2024年 野村不動産ホールディングス 執行役員(DX推進統括)を経て、2025年4月より現職の野村不動産ホールディングス株式会社 参与。
1990年大手米国年金基金との米国不動産投資を開始し、1997年からは日本の不動産投資に着手、2001年不動産私募ファンド運用のため、野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社設立。2002年には日本の運用会社による初めてのオポチュニティファンドである日本不動産オポチュニティ・ファンド(JOFI)の組成・運用を手がける。2004年以降、同社の安定型不動産私募ファンド(Smileシリーズ)の組成に携わり、2005年野村不動産投資顧問株式会社を設立、不動産証券化商品への投資に着手。2010年私募REIT第一号を運用開始。2013年野村不動産にてCREを中心とした法人営業を担当。2015年野村不動産アーバンネットにて仲介・CRE部門の企画を担当。(2021年4月1日より「野村不動産ソリューションズ」に社名変更)、同社のデジタルマーケティング、DX戦略を推進。2024年野村不動産ホールディングスにて、グループ全体のDX戦略推進を担当。
宅地建物取引主任者、日本証券アナリスト協会検定会員
第四回5月28日
テーマ
ラグジュアリービジネスのいま
講師金山 明煥
東急株式会社 執行役員
講師セオドア・言・ニフィング
Plus Curiosity 創業者・代表取締役
第四回目は、金山明煥先生、セオドア・言・ニフィング先生による講義「ラグジュアリービジネスのいま」が行われました。講義では、まずラグジュアリーのキーワードとして、論理ではなく感情に訴える付加価値や、いまここでしかできない体験といった視点が示されました。次に、現在ラグジュアリーの領域は「モノ」「体験」「ライフスタイル」の3つに分けられ、ラグジュアリーブランドの戦略は、より後者の領域へとシフトしていることが説明されました。併せて、顧客層の若年化・多様化や、フィジカルな空間で体験を提供する上での不動産の重要性についても触れられました。講義の最後は、都市開発にラグジュアリーをどのように取り入れるかについて、実際の開発事例を交えた説明で締めくくられました。
【塾生の声】
「マスへの迎合は価格競争を引き起こし、経営効率を下げることにも繋がる」という言葉が印象的でした。ビジネスとして取組む以上は規模の議論が不可欠で、マスを優先する思考に偏りがちです。しかしながら「ラグジュアリー」に求められる希少性は、マスの対極にあるとも言えます。ビジネスにおいて、希少性と普遍性のバランスを取っていく為に、どのように取り組んでいく事ができるのか。難しい話ですが、だからこそ、うまくはまれば得られる果実も大きいのだと思いました。(40代・ホテル事業)
ラグジュアリーとは何だろうか。これ迄は、サラリーマンマインドからIRR等の投資指標にとらわれ、アートや文化等効果が見えにくい価値について思い切って考えたことはなかった。講義の中で「日本は1泊5万円のホテル“は”クオリティが高い」という話があったが、インバウンド消費、特にアッパー層のニーズを掴むためには、これまでのマインドを改める必要があると強く感じた。一方で、日本の資源を活かすことで彼らにとっての真のラグジュアリー「一生に一度きりの特別な体験」を提供する余地は十分にあるとも感じたので、数字で測れない世界観にも向き合っていきたい。(30代・金融業)

東急株式会社 ホテル・リゾート事業部 執行役員。早稲田大学(建築学専攻)卒業後、東急建設株式会社に入社。その後、マサチューセッツ工科大学に留学し修士課程(都市計画およびマネジメント)修了。帰国後、東京急行電鉄株式会社(現、東急株式会社(以下、「東急」)に転籍し、東京大学博士号(都市計画)取得。東急では、組織再編、リテール事業、不動産事業、およびホテル事業など多岐事業に従事し、株式会社東急ビッグウィーク(タイムシェアリゾート事業)および株式会社THM(新宿2ホテルオーナー事業)の代表取締役社長を歴任して現職に至る。また、留学中よりULI(Urban Land Institute)に所属し、日本におけるULI設立時の創設メンバー。

2018年に東京でプラス・キュリオシティを立ち上げる以前は、香港を拠点にCushman & WakefieldのAPAC地域リテール部門責任者を務めた後、アジア・中東のショッピングセンター・デベロッパーへのアドバイスやプレイスメーキングに特化したコンサルタント会社であるHusband Retail ConsultingのCOOを歴任した。また、上海に5年間駐在し、Appleの地域リテール拡大担当を経て、Cushman & Wakefieldの中国リテールリース事業の責任者として貢献した。セオは東京出身の日米ハーフである。
第三回-第1部5月14日
テーマ
働き方×ワークプレイス
ザイマックス総研のリサーチから
講師石崎 真弓
ザイマックス総研 主任研究員
第三回目は、2名の講師による2部構成で、第1部では石崎真弓さんによる講義「働き方×ワークプレイス ザイマックス総研のリサーチから」が行われました。講義は、最初に塾生に向けて今どのような働き方をしているか、その働き方に満足しているかの問いかけから始まりました。その後、ザイマックス総研が公開した働き方に関するレポートをもとに、コロナ禍前後のワークプレイスや働き方の変化の説明や、現在のオフィスの課題と見られる点や今後のワークプレイス戦略についての考察が示されました。最後は、最近の工夫されたワークプレイスの事例や、グローバルな視点での東京の競争力についての説明が行われ、講義が締めくくられました。
【塾生の声】
時間軸を長く取ると、いつからか誕生した間接部門が拡大、人を集めるために出現したオフィスについては、近年まで「人数」が最大のボトルネックであった。そこから、ITの進展により、この「人数」の制約が緩和されたことで、自由度が高まり、オフィスがあたかもソフトのようになってきたことは興味深い。講義を受けて、塾生自らもオフィスのスタディツアーを企画、論理と実践を通じて深い理解につなげることを予定している。この「実践」も可能な本塾の良さを存分に享受し、さまざまなテーマにおいて、一歩でも二歩でも手触り感のある学びを積み上げていきたい。 (40代・金融業)
「講義を通して、オフィスとして従来のようにただ床を貸し出すだけでなく、生産性向上やコミュニケーションの活性化、従業員のモチベーション向上等に寄与するオフィスの重要性が益々高まってきていることを痛感しました。コロナ禍を経てリモートワークをはじめとした多様な働き方が広がる中、より付加価値の高い、ワーカーに選ばれる場所を提供することで、社会全体での生産性向上に寄与できればと、不動産業界にいる一員として思いました。 (30代・不動産投資業)

リクルート入社後、リクルートビルマネジメント(RBM)にてオフィスビルの運営管理や海外投資家物件のPM などに従事。2000年RBMがザイマックスとして独立後、現在のザイマックス総研に至るまで一貫してオフィスマーケットの調査分析、研究に従事。近年は、働き方と働く場のテーマに関する調査研究、情報発信している。日本ファシリティマネジメント協会、オフィス学会、テレワーク協会、テレワーク学会また日本サステナブル建築協会知的生産性研究コンソーシアムに研究参加。
第三回-第2部5月14日
テーマ
技術・社会の未来予測と建築不動産産業へのインパクト
講師河瀬 誠
立命館大学(MBA)教授 / MK&Associates 代表
第2部では、河瀬誠先生による講義「技術・社会の未来予測と建築不動産産業へのインパクト」が行われました。講義では、デジタル技術の急速な進化により、多くの「新常態」が常識へと転換しつつあり、20年後には現在では考えられないことが当たり前になる可能性が示唆されました。続いて、デジタル技術の進化とともに建設業のロボット化や人口動態、世代間の価値観の変化、シェアエコノミーといった産業・生活両面での変化が起こっていることが紹介されました。最後は、都市の主役を車から人へという視点に基づいた、従来の常識とは異なる新たなまちづくりの事例が提示され、「未来の妄想から出発して、今後の都市を考えてほしい」という言葉で締めくくられました。
【塾生の声】
今回の講義を通じて、デジタル技術の進化が社会・都市・生活に与える影響を改めて実感した。特に、ムーアの法則に基づく加速度的な技術の進歩が今後業界の破壊をもたらすという内容は大きな衝撃であった。環境の変化に対応した組織作りと、本質的な価値を磨き続ける努力の重要性を学ぶ良い機会となり、視座を高く持つことの必要性を再認識した。 (20代・総合デベロッパー)
デジタル/テクノロジーがいかに我々の社会や生活を変えているかについて学び、その指数関数的な変化のスピードを踏まえると、今の常識を前提に未来を考えることは適切ではないという点を痛感しました。また、社会のニーズや価値観の多様化を踏まえ、ビジネスが提供するプロダクトは、今後いかにニッチな点を攻めていけるかが重要、という点も講義の中で印象的なポイントでした。大きい組織、会社であればあるほどマスにアプローチする必要がある一方で、金太郎飴的な再開発ビルが集客等に苦戦しているような事例を見ると、不動産業界にとっても当てはまる重要なポイントではないかと感じました。 (30代・不動産ファンド)

東京大学工学部計数工学科卒業。ボストン大学経営大学院理学修士および経営学修士(MBA)修了。A.T.カーニー、ソフトバンク、ICMGを経て、現職。著書に『知的資本経営入門』(生産性出版)、『未来創造戦略ワークブック』『経営戦略ワークブック』『戦略思考コンプリートブック』『新事業開発スタートブック』『海外戦略ワークブック』(以上、日本実業出版社)『戦略思考のすすめ』(講談社現代新書)『マンガでやさしくわかる問題解決』『課題解決のレシピ』(日本能率協会)などがある。
第二回4月16日
テーマ
不動産市場の未来:未来の不動産市場のリスク
講師清水 千弘一橋大学教授・麗澤大学副機構長学長補佐
第二回目は、当塾のアドバイザーでもある清水千弘先生による講義「不動産市場の未来:未来の不動産市場のリスク」が行われました。講義は、2017年に予測された、未来のアメリカの不動産市場のレポートに基づき、当時の予測が実際に正しかったのか、また日本ではどうであったのかを軸に、予測された要素に関連する研究を紹介する形で進められました。研究事例としては、人口減少と都市への集中による日本の人口分布の変化、人口減少・高齢化・国際化が不動産価格に与える影響、不動産バブル崩壊のプロセスなどの研究が取り上げられました。講義の最後は、「30年後のリスクを予想し、それをコントロールして未来を作る議論をしてほしい」という言葉で締めくくられました。
【塾生の声】
清水先生の講義を通して様々な観点から不動産の未来を予測可能であることを学んだが、近年、建築物の老朽化対策、空き家問題等のリスクに着目しがちであり、人の感情や、技術革新の動向に着目した政策がなかなか進んでいないように思う。今後、限られたリソースで未来について考えていくには、リスクを全て解消しながら進んでいくのか、割り切って進むのか、岐路に立たされているため、未来のビジョンを強く掲げ続けることに必要な判断力を磨くにあたり、自分自身学び続けていきたいと感じた。(20代・公務員)
不動産業界の構造的課題や、人口動態・地域衰退といった大きな社会的テーマと不動産の関係性について深く考える機会をいただきました。普段の実務では得られない理論的な視点や、先進的なデータ活用の事例にも触れることができ、非常に刺激的な時間となりました。(30代・総合デベロッパー)

一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科教授、麗澤大学学長補佐 国際総合研究機構長、清華大学不動産金融センター顧問。東京大学博士(環境学)。プリティッシュ・コロンビア大学、シンガポール国立大学、香港大学 客員教授、マサチューセッツ工科大学Research Affiliate、麗澤大学経済学部教授、日本大学教授、東京大学特任教授を経て現職。専門は、指数理論・ビッグデータ解析・不動産経済学。主な著者に、『Property Price Index』Springer(共著)(2020)、『日本の物価・資産価格』東京大学出版会(渡辺努氏と共編(2023))など多数。Member of CRE。
第一回4月9日
テーマ
開講式・不動産の見方、考え方
講師中山 善夫ザイマックス総研 代表取締役社長
からくさ不動産みらい塾第九期がスタートしました。今期は様々な業種から20名の塾生の参加となりました。最初に開講式が行われ、中山塾頭から、からくさ不動産みらい塾の設立からリニューアルまでの背景・経緯や、これまでの塾生達の様子などを伝え、塾生達への期待を述べる挨拶が行われました。その後、中山塾頭による第一回目の講義「不動産の見方・考え方」が行われました。講義では、最初に不動産とは何か?という話がされ、続いて時代に応じて不動産の使われ方が変化する中、世の中と不動産のこれからを考える上で重要な視点についての説明が行われました。講義の最後は「飛耳長目」を大事に、1年間を頑張ってほしいという塾生たちへのエールが送られ、第1回目講義が終了しました。
【塾生の声】
第一回の講義では、不動産はお金儲けの手段ではなく、大切な資源であり、国そのものであることなど、不動産の本質的な価値について、多くの気づきを得ました。 普段の業務ではどうしても収益性に注目しがちですが、もっと高い視座で不動産を見て、どう「みらい」を作っていくべきなのか、塾の仲間たちとこの1年間議論できることにワクワクしています。(30代・不動産業)
創設の背景、中山塾頭の熱い思いを伺う中で、不動産に何らかの形で携わっているこの志高いメンバーと1年間、様々なことを学び不動産業界に何らかのインパクトを与えられるように奮闘したいという思いが強まった。1回目の講義を受講して、不動産が関係しない業界はないので、不動産以外の分野の知見を深めることで一層不動産への理解が深まるのではないかと感じた。(20代・総合不動産サービス業)

株式会社ザイマックス総研代表取締役社長。ニューヨーク大学大学院不動産修士課程修了。一般財団法人日本不動産研究所で数多くの不動産鑑定・コンサルティングに従事。その後、ドイツ証券にてドイツ銀行グループの日本における不動産審査の責任者を務める。2012年よりザイマックスグループの役員に就任、現在、ザイマックス総研にて不動産全般に係る調査研究を担当。不動産鑑定士、MAI、CCIM、Fellow of RICS、Member of CRE。ARESマスター「不動産投資分析」科目責任者、不動産証券化協会教育・資格制度委員会委員。