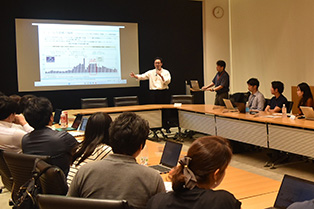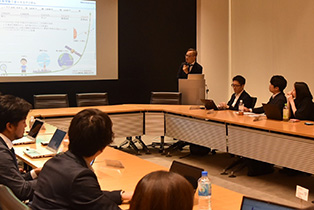活動報告(第九期)
- REPORT

第十九回-第1部1月21日
テーマ
街とデジタルの融合による価値の創出を考える
講師川崎 麻美子
NTTアーバンソリューションズ(株) 街づくり推進本部 デジタルイノベーション推進部 担当課長
第十九回目は、2名の講師による2部構成で、第1部ではからくさ不動産みらい塾1期生でもある川崎麻美子先生による講義「街とデジタルの融合による価値の創出を考える」が行われました。講義では最初に、不動産分野にデジタル技術を活用する過程で直面する、現場の負担増やデジタル側と不動産開発の間での時間軸の違いといった課題が語られました。続いて、不動産分野でのデジタル活用をスケールさせるため、ハードに制約されないデジタルの特徴を既存事業と接続させる重要性がメタバースやARを活用した事例とともに説明されました。最後は、既存領域の効率化だけでなく、デジタル技術を活用した新しい価値創出を通じて、次世代にとって魅力的な不動産業の未来を作っていく必要性が説かれ、講義が締めくくられました。
【塾生の声】
私自身デジタル・DXというと既存業務や機能の代替にとらわれてしまいますが、川崎さんの内閣府でのスーパーシティ構想推進の取り組みや品川港南エリアでのデジタルと空間の融合の事例を伺う中で、将来の街の姿からバックキャストして実現したいワークスタイルをデジタルで形にしていく姿にハッとしました。投資にあたっては短期間での投資回収が求められますが、運用・使う人を含めて「使って育てていく」長期的な視点の重要性も学びました。 (30代・金融業)
不動産業界へのデジタル導入という難題に対し、既存の延長ではない「サービスへの昇華」という視点をどう取り入れていくかを体験談を交えて語っていただき大変参考になりました。特に「中堅世代が次世代に夢を見せる」という言葉に強く感銘を受けました。社内外を巻き込む苦労もリアルでしたが、懇親会での深い議論を通じ、挑戦していくことの重要性を改めて感じました。この学びを次世代に繋ぐ価値創出へと繋げていきたいです。 (20代・リネンサプライ業)

2007年NTT都市開発株式会社入社。分譲住宅事業、PM業務、法人営業、経営企画部・広報に従事。
内閣府地方創生推進事務局へ出向、国家戦略特区・国際・広報業務に係る。
2018年に設立したNTTアーバンソリューションズへ転籍。
NTTグループの不動産アセット・技術ソリューションを生かしたエリアの価値向上及び新規価値創出に取り組む。
第十九回-第2部1月21日
テーマ
“JAPAN HOTEL STORY”背景と展望
講師沢柳 知彦立教大学観光学部 特任教授 / (株)ブレインピックス 代表取締役
第2部では、沢柳知彦先生による講義「“JAPAN HOTEL STORY”背景と展望」が行われました。最初に、日本のホテル市場におけるインバウンド需要の現状として、好調を維持しているものの、円高リスクや交通インフラのキャパシティ不足など、今後の成長を阻害する懸念材料が示されました。続いて、日本のホテル業界では大手チェーンによる規模の経済が働かず、労働生産性の向上やホテル経営人材の育成が遅れている構造的な課題が語られました。最後は、最近のホテルではオーナーとオペレーターとの緻密な利害調整の重要度が増しており、オーナーにとって、現場の業務改革にまで踏み込むことが求められるオペレーショナルアセットへと変化してきていることが説明され、講義が締めくくられました。
【塾生の声】
日本のホテルは海外と比べてチェーン化が圧倒的に進んでおらず、上位ホテルであっても全体のわずか4~5%しか占めていないという事実に大変驚きました。さらに、今後の少子高齢化による人手不足や、インバウンド需要が今後も右肩上がりで、伸び続けるとは限らないことを踏まえると、従来のやり方では生き残ることが難しくなっていくと感じます。したがって、コスト効率を高める工夫や、他社にはない圧倒的な差別化を図る取り組みが一層求められており、日本のホテル経営はまさに転換点を迎えているのだと強く実感しました。 (30代・金融業)
インバウンドの回復や円安で追い風が吹く一方、二次交通や人手不足といった足元の課題も丁寧に示され、日系OPの勝ち筋は量から質へという流れが腑に落ちました。外資チェーンの存在感と日本勢の差別化・コストの工夫、オーナーの資産の見方もわかりやすく、多面的にホテルアセットをみることができた講義でした。 (30代 不動産業)

1987年日本長期信用銀行入行。国内企業M&Aアドバイザリー業務を経て海外ホテル投資会社に出向。その後、外資系証券会社を経て2000年にジョーンズラングラサールのホテルズ&ホスピタリティグループ東京オフィス代表に就任。同社日本法人の執行役員、取締役を歴任し、2020年6月退職。同年(株)ブレインピックス設立、代表に就任。マンダリンオリエンタル東京、リッツカールトン東京などの契約交渉支援、IHG-ANAホテルズグループのJV組成支援、ANAホテルポートフォリオ、トマムリゾートなどの売却支援を主導。現在、(株)せとうちクルーズ社外取締役、一橋大学大学院経営管理研究科非常勤講師、立命館大学大学院経営管理研究科客員教員(令和6年度より)も務める。
第十八回1月7日
テーマ
“ディベロッパー”の再定義へ向けて
講師林 厚見株式会社スピーク共同代表 /「東京R不動産」ディレクター
第十八回目は、林厚見先生による講義「ディベロッパーの再定義に向けて」が行われました。講義では、最初にビジネスとクリエイティブを横断する視点から、不動産をセレクトショップのように仲介する「東京R不動産」や使い手による主体的な空間作りをサポートする「ツールボックス」等の活動が紹介されました。あわせて、ディベロッパーの新しいあり方として、使い手が主体的にまちづくりに関わることを支援する「ソーシャルディベロッパー」という考え方が提示されました。続いて、ゲスト講師の田澤悠先生より、アーティストや地域の芸術コミュニティの支援を目的に、宿泊費の一部をアーティストに還元するBnAの取り組みが解説されました。最後は、短期的な利益だけでなく長期的なストーリーを考え、持続可能な不動産ビジネスを作ってほしいという受講生へのエールで締めくくられました。
【塾生の声】
「ディベロッパーとは何か?」、林様からひたすら「問いかけ」をいただく講義であった。これまでと異なり、これからのディベロッパーは、人口減・建築費等の高騰などの制約もあり、今あるAssetを壊さずに、効率的に運用管理し、新たな価値を生み出すモデルを模索している。エリア・建物の所与の条件はさまざまであり、結果としてそれが個性、魅力になっている開発事例が多く生まれている。林様のおっしゃるように、実は会社がディベロッパーなのではなく、一人ひとりがディベロッパーとなり、自らがかかわるエリア・建物に責任を持つようになることで、自然と魅力的な街が生まれ、維持されるのかもしれない。(40代・金融業)
「ディベロッパーの再定義」という新たな切り口の講義を通じ、R不動産の取り組むソーシャルディベロプメントこそ人口減少時代のデベロッパーに不可欠な概念だと確信した。大手では困難な「コーポラティブビレッジ」のようなコミュニティ形成を、経済性と両立させようと工夫する姿勢に強く感銘を受けた。コミュニティ形成、社会性の追求をいかにビジネスとして成立させるかという問いは、自身の今後のキャリアにおいても追求すべき重要なテーマと感じた。(30代・不動産ファンド)

1971年東京生まれ。東京大学工学部建築学科(建築意匠専攻)、コロンビア大学建築大学院不動産開発科修了。経営戦略コンサルティング会社マッキンゼー& カンパニー、国内の不動産ディベロッパーを経て現職。不動産のセレクトサイト「東京R不動産」、空間づくりのウェブショップ「toolbox」のマネジメントのほか、建築・不動産の再生に関わる事業企画・設計デザイン、地域再生支援、宿泊施設・飲食店舗・広場などの運営を行う。東京大学工学部、早稲田大学創造理工学科等の非常勤講師、東京都築地再開発専門委員、グッドデザイン賞審査委員などを歴任。共編著書に『東京R不動産2』『だから、僕らはこの働き方を選んだ』『toolbox 家を編集するために』『2025年の建築 新しいシゴト』等。
第十七回-第1部12月10日
テーマ
人手不足問題と日本の未来
講師古屋 星斗リクルートワークス研究所
第十七回目は、2名の講師による2部構成で、第1部では古屋星斗先生による講義「人手不足問題と日本の未来」が行われました。最初に、現在の日本の労働市場は景気変動に関わらず慢性的な人手不足にあり、その背景には高齢化に伴う人口動態の変化があることが示されました。続いて、人手不足の影響はゴミ収集などの地域サービスから顕在化し、今後は生活維持に追われ仕事どころではなくなる懸念があること、また労働供給の限界が賃金・設備投資額・物価の上昇を招く「令和の転換点」を迎えていることが語られました。最後には、人手不足に対応するDXの進め方に加え、世界に先駆けた社会構造の変化を機会と捉えてほしいというエールで講義が締めくくられました。
【塾生の声】
景気と無関係に続く「構造的な人手不足」の真因が、85歳以上の急増と単身世帯化にあるという分析は印象的でした。一方で、IT人材だけでなく「現場の知恵」と技術を掛け合わせる解決策には希望を感じます。独居高齢者向けのモビリティや娯楽といった「新市場」の視点も斬新で、前回の不動産の話と合わせ、課題をビジネスチャンスに変える重要性を学びました。 (30代・総合テベロッパー)
「人口動態は確実な未来予測」という言葉に強く共感しました。人手不足は日本が世界に先駆けて直面する危機ですが、同時に大きなビジネスチャンスでもあります。特にエッセンシャルワーカーの領域では、現場実務への深い理解とITを掛け合わせる「現場参謀」的な視点が解決の鍵になると学びました。現場実務と技術を融合させ、いかに新たな価値を創出していくか。これからの不動産ビジネスにおいても不可欠な視座として持ち続けたいです。 (40代・ホテル事業)

2011年一橋大学大学院社会学研究科 総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定等に携わる。2017年より現職。労働市場分析、組織・人材研究を専門とする。内閣官房地域働き方・職場改革等推進会議構成員。大阪府学校教育審議会審議員。早稲田大学教育・学術研究院非常勤講師。
著書に「なぜ『若手を育てる』のは今、こんなに難しいのか」(日本経済新聞出版2023)、「『働き手不足1100万人』の衝撃」(プレジデント社2024)、「会社はあなたを育ててくれない」(大和書房2024)など。
第十七回-第2部12月10日
テーマ
社会課題から新規ビジネスを考える~ザイマックス流の事業創造~
講師中道 大輔ザイマックス 執行役員
第2部では、中道大輔さんによる講義「社会課題から新規ビジネスを考える」が行われました。最初に、新規ビジネスの要諦として、社会課題をむしろ積極的に「利用する」という発想が示されました。続いて、ホテルの不満解消やリネン業界の脆弱な下請け構造、物流の「2024年問題」に伴うホテル内搬送の負荷など、深刻な課題をあえて強みと結びつけることで収益化を図る具体例が語られました。その中では、解決が困難な課題を利用したビジネスには、持続的な利益を生める、競合の少ない領域で勝負できるといった特徴があることが説明されました。最後は、日常の違和感から不安や不便などの「不」を見つけ出すことでビジネスを構想してほしいというエールで講義が締めくくられました。
【塾生の声】
新規ビジネスの創出プロセスについてSWOT分析の強み×社会課題で捉えるという新しい発想を学ぶことができ、とても刺激になった。特に需要と供給のギャップが儲かるという視点は重要な視点であるとともに「踏み込む勇気」にも非常に感化された。コンテツが飽和していてギャップを感じにくい現代でも、長期的な視点で未来を見据え、推測することでギャップを見つけられると感じたためその視点を忘れず日々に活かしていきたいと思う。 (30代・小売業)
自社の強みを分析した上で「社会課題」(SWOTでいう脅威)を起点に新規ビジネスを創出するという考えが印象的であった。社会課題は簡単に解決できないからこそビジネスとしての継続性があり、そこにブルーオーシャンの事業機会があるという観点、「不は儲かる」「発明より発見」など日常的に意識することで生まれてくるアイディアや視点が大いにあると感じ、非常に興味深い講義であった。 (30代・不動産業)

株式会社ザイマックスグループ リネン事業担当執行役員。
1996年大学卒業後、広告会社、ウェディングドレス製造会社経営を経て2019年当社入社。入社以来当社にとっては新規事業となるリネン事業に従事。京都大学経済学部卒 神戸大学MBA
第十六回-第1部11月26日
テーマ
FM視点から見るオフィスとオフィスビルのゆくえ
講師似内 志朗ファシリティデザインラボ代表
第十六回目は、2名の講師による2部構成で、第1部では似内志朗先生による講義「FM視点から見るオフィスとオフィスビルのゆくえ」が行われました。講義では、最初に環境負荷の最小化とウェルビーイングの最大化の両立がファシリティマネジメント(FM)の究極的なミッションとして示されました。特に、人件費はファシリティコストの約10倍であるという分析に基づき、オフィスは単なるコストではなく、人的資本最大化のための投資として捉える必要性が強調されました。講義の最後は、アダプティブ・リユース(適応的な再利用)が、建設費や工期の削減、エンボディード・カーボン削減、時間資産の活用といった側面で有効な手段であるという提案で締めくくられました。
【塾生の声】
本講義では、身近でありながら、存外、理解していないFM業務について、郵政関係の建築物の設計・企画・管理を行ってきた講師より、設計意図を踏まえたPDCAを回すことと教えて頂き、大変目からうろこが落ちる思いでした。また、FM業務の思想についても、時代の流れによる変化があることも新鮮な驚きでした。FM業務の価値を再評価し、開発にフィードバックをすることも考えられるなど、一連のプロセスとして整理し直すことの重要性を学びました。(40代・法律事務所)
オフィスビルは人材を惹きつける場所に変わっていく、というワードが印象に残りました。コロナでオフィス離れが進むと思いきや、結果を見ればオフィス回帰となっており、ただ働く場所だったものが、より生産性を高める場所だったり、人を集めるためのシンボルになっていると感じます。他方でまた何かのきっかけでこの流れが変わることもあると思うので、時代に合わせ、より良いあり方を常に考えなければいけないと感じました。(30代・不動産業)

北海道生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業、ロンドン大学(UCL)バートレット建築校修了。郵政省・日本郵政グループで建築設計・ファシリティマネジメント・事業開発・不動産開発企画と担当。日本郵政(株)事業開発部長、不動産企画部長等を歴任。2019日本郵政(株) 退職後、ファシリティデザインラボ代表、(株)イトーキ社外取締役、(株)ヴォンエルフ シニアアドバイザー(2019-2023)、JFMA理事・フェロー・調査研究委員会委員長、筑波大学客員教授、東洋大学非常勤講師等。
第十六回-第2部11月26日
テーマ
企業における不動産戦略と不動産テックの動向
講師板谷 敏正株式会社プロパティデータバンク 代表取締役会長
第2部では、板谷敏正先生による講義「企業における不動産戦略と不動産テックの動向」が行われました。講義では最初に、不動産の長期的な価格上昇や建物の寿命といった動向や、各企業がバランスシートや事業戦略に基づく多様なCRE戦略を実践していることが解説されました。続いて、講義の主題である不動産トランスフォーメーション(ReX)の考え方について紹介されました。これは「空間の変革」と「ビジネスモデルの変革」の組み合わせとして定義され、都市での大規模再開発や、既存ストック利活用、不動産のサービス化といった具体的な変革の事例とともに示されました。最後に、ReXを支える基盤として、BIMやデータサイエンスといったIT技術活用の重要性が解説され、講義が締めくくられました。
【塾生の声】
前半の建物寿命について、解体をされた建物を利用した寿命の統計と課税対象の建物の統計では基準とする対象物により大きく数値が異なるため、グラフの横軸・縦軸が何を対象・基準としているかという目線を持つことが必要であることを学んだ。後半のBIMを活用した施設管理について今後普及することで、従来の図面にプロットするようなアナログな業務がなくなり、各社(オーナー、管理会社)の確認作業も減ることで業務効率化がなされ、ビルの価値向上に注力できると感じた。 (20代・総合不動産サービス業)
本講義では、国富の三割を不動産が担う現実を踏まえ、CRE戦略と不動産テック(DX)を軸に、長寿命化・用途転換・官民連携によりROAと社会的価値を同時に高めることの重要性を学んだ。特に静岡県のような自治体は資産の約93%が固定資産であり、公的不動産の運用改善が必須で、DXによる可視化・最適化と発想の掛け合わせが鍵である点がとても勉強になった。 (20代・総合デベロッパー)

早稲田大学大学院理工学研究科修了、清水建設株式会社入社。2000年、社内ベンチャー制度を活用し、不動産管理向けクラウドサービスを展開するプロパティデータバンク株式会社設立、代表取締役就任。2022 年4月より代表取締役会長に就任。09年には最も優れた経営戦略を実践する企業として“ポーター賞”を受賞。18年には東京証券取引上マザーズ市場に上場。その他国交省「企業不動産の合理的な所有・利用に関する研究会」委員、「不動産ID・EDI研究会(2007)」委員、日本ファシリティマネジメント協会理事、株式会社丹青社社外取締役などを務める。芝浦工業大学 客員教授(2010年~2021 年)、早稲田大学大学院創造理工学研究科 客員教授を兼任。博士(工学)
<主な著書>
CRE戦略と企業経営(東洋経済新報社)、次世代建設産業戦略2015(日刊建設通信)、不動産トランスフォーメーション(幻冬舎)
第十五回11月12日
テーマ
生活すべてがオリエンだ ~未来をひらく発想法~
講師石寺 修三公益財団法人 博報堂教育財団 常務理事補佐
第十五回目は、石寺修三先生による講義「生活すべてがオリエンだ~未来をひらく発想法~」が行われました。講義では、最初に仕事のオリエンをする人(≒依頼者/発注者)は消費者であり、消費者をよく知るためには、その背景にある生活者としてその暮らしを多面的に捉える必要があるという考え方が示されました。続いて、生活者視点に立ったオリエンのケーススタディとして、生活定点調査の数値の変化とその背景や、高齢者の冷蔵庫が大量の物で溢れるという問題を解決する方法などのテーマで塾生同士での意見交換が行われました。最後は、「生活の全てがオリエンと考え、見聞きする事実全てを発想の源にしてほしい」という言葉で締めくくられました。
【塾生の声】
「生活すべてがオリエンだ」とのタイトルの通り、生活者として過ごす際のあらゆる視点が、仕事上のインサイトにつながるのだと学びました。日々の体験について「なぜ良いと思ったか、違和感を覚えたか」を深掘りすることを習慣づけたいです。また、自身と世間の感覚の乖離や、非凡子からブレイクスルーを得るという視点も大変勉強になりました。過去、現在を通して今後の未来を予測、創造していけるよう、業務に活かしたいです。(20代・ホテル事業)
「不動産の未来を決めるのは生活者である」というメッセージに衝撃を受けた。本来取り組まなければいけない「真ん中に人がいる街づくり」が疎かになっていると痛感したからだ。また、講義では生活者の視点に立ち、普段接している賃料データ等ではなく、足で稼いだ街のデータ、「かわいい」という言葉、「独身高齢女性の冷蔵庫」の写真から連想し、街づくりのアイディアやビジネスを創出していくアプローチ等を紹介いただき、目から鱗でした。(40代・デベロッパー)

1989年に博報堂入社。マーケティング・プラナーとして市場調査や商品開発、コミュニケーション業務に従事。以後、ブランディングや新領域を開拓する異職種混成部門やスタッフ職の人事・人材開発部門を担当。2015年~2024年は博報堂生活総合研究所長として、博報堂グループのフィロソフィーである「生活者発想」を軸とした調査研究に従事し、2025年より現職。著書:『生活者の平成30年史 ~データで読む価値観の変化~』(共著・日本経済新聞出版・2019年)、『地ブランド~日本を救う地域ブランド論~』(共著・弘文堂・2006年) 法政大学 非常勤講師
全体懇親会10月29日
10月29日、第1期から第9期までの全塾生に呼びかけた「からくさ不動産みらい塾全体懇親会」が開催され、合計75名の卒塾生・塾生が参加しました。懇親会は、中山塾頭の挨拶と乾杯のご発声から始まりました。懇親会の中では、塾生・卒塾生による近況報告や、塾の活動報告・企画への呼びかけなどを交えながら、同期同士の旧交を温める場となりました。また、異なる期の塾生同士の新たな交流も生まれ、より大きな業界ネットワークが形成される機会となりました。最後は、アドバイザーの清水千弘先生による、「これからも世代交代もしながら持続的なネットワークを作ってほしい」という締めのご挨拶で、盛会のうちに終了しました。
第十四回-第1部10月15日
テーマ
データ利活用型まちづくり ~建築・街区・都市のDX~
講師川除 隆広日建設計総合研究所 役員 主席研究員 麗澤大学 客員教授
第十四回目は、2名の講師による2部構成で、第1部では川除隆広先生による講義「データ利用活用型まちづくり」が行われました。講義では、最初にデータ利活用型まちづくりを行う上での基本となるデータ分析の方法、およびその結果の解釈と活用法について説明がありました。次に、建築・都市計画におけるデータ利活用の最新動向として、3D都市モデル「PLATEAU」や都市計画GISデータのオープン化、GPSや購買情報といった民間データの活用などが、具体的なユースケースとともに紹介されました。最後に、未来のデータ利活用型まちづくりの方向性が紹介され、「データを活用して地域の価値を高める考え方がスタンダードになっていく」という言葉で講義は締めくくられました。
【塾生の声】
今回の講義では、国交省が主導して作成する不動産に関する様々なオープンデータの存在を知るとともに、自分が通常の業務にいかにデータを生かせていないかを痛感しました。また、印象的なのはWalkability Indexのスライドで、単純に色々なデータを見るだけでも面白いですが、特にデベロッパーにとっては事業の効果測定にも有用なのではないかと感じました。「まちづくり」という言葉が一人歩きしがちですが、実際にこう言った定量的な分析に基づき地域への貢献度を図ることもできると考えます。(30代・デベロッパー)
現在でも情報が溢れていると感じていましたが、講義を通じ、実際にはまだ情報活用の黎明期にあり、今後さらに多様なデータが増加していくことを実感しました。今後は必要な情報に迅速にアクセスできる仕組みづくりや、各所が整備するオープンデータやシステムの周知が重要であり、また、まちづくりには多様な組織が関わるため、それぞれのデータを有機的に連携させ、相互に活かしていくことが求められると感じました。(30代・不動産業)

1995年東京理科大学大学院修士課程修了。2001年京都大学大学院博士課程修了。博士(工学)。技術士(総合技術監理部門・建設部門)。専門は、都市計画、都市情報分析、事業評価、官民連携事業など。総務省ICT街づくり推進会議スマートシティ検討WG構成員、総務省データ利活用型スマートシティ推進事業外部評価委員、内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」のうち「アーキテクチャ構築等」採択審査委員、国土交通省/データ駆動型社会に対応したまちづくりに関する勉強会委員、CASBEE都市検討小委員会委員、CASBEE街区検討小委員会幹事などを務める。著書に「ICTエリアマネジメントが都市を創る」、共著に「スマートシティはどうつくる?」、「駅まち一体開発 TOD46の魅力」、「不動産テック」などがある。
第十四回-第2部10月15日
テーマ
オフィスの未来を考える
講師山方 俊彦ザイマックス総研 主任研究員
第2部では、山方俊彦さんによる講義「オフィスの未来を考える」が行われました。 講義ではまず、現在までの東京オフィスマーケットの動向の振り返りと、オフィスマーケットを正しく理解するためのマーケット指標の読み解き方についての説明が行われました。その後、「働く場所が多様化した中、オフィスは何を担うべきか?」や、「”高くても選ばれるオフィス”の条件とは?賃料はいくらになる?」など、オフィスの未来に関する4つのテーマについて塾生を交えた議論が行われました。議論では、「企業によってオフィスの定義が多様化していく」、「オフィス単機能ではなく、多様な用途のある場所が選ばれるようになる」など、多様な意見が交換されました。
【塾生の声】
講義の中で語られていた「その情報って本当なの?と疑え」という言葉が、特に印象に残りました。現代は情報やデータがあふれている時代ですが、それらの言葉が意味する内容を十分に理解せずに鵜呑みにしてしまうと、判断を誤る可能性があります。たとえ新聞の記事であっても、正しく判断できる知識を身につけることはもちろん重要ですが、それ以上に「本当なのか?」と問い直す視点こそが、より大切だと感じました。日々の業務で扱う言葉や情報も、意味を取り違えることで投資判断を誤るリスクがあります。不動産の未来を考える上でも、この視点は非常に重要であると、改めて気づかされました。 (30代・金融業)
前半は講義、後半は事前に与えられたテーマの発表・共有という形で行われ、これまでの塾の講義を通して考えてきた、不動産市場全体や技術・社会の未来予測などを個人的にも振り返りながら臨んだ回となりました。また、これまで同じ講義を聞いてきても、塾生其々の見解は違っていたりもして、大変刺激を受けました。これから確実に変わっていくオフィスマーケットについて、当日にあがった意見等も思い出しながら、今後に注目していきたいと思います。(30代・不動産業)

1991年日本生命保険入社。不動産部にて投資用不動産の運営実務に携わり、1997年にニッセイ基礎研究所出向。オフィスマーケットの調査研究に従事。2003年ザイマックス入社。マーケティング部で不動産のデューデリジェンス等に従事し、2013年から現職。
不動産マーケットの調査分析・研究を担当。不動産証券化マスター。不動産証券化協会・資格教育小委員会分科会委員、市場動向委員会委員長(2023~24)・副委員長(2025~)。不動産証券化マスターテキスト103「不動産投資の基礎」第3章「指標の見方」を執筆担当。論文(共著)「空室率と募集賃料の時系列データに基づく東京23区オフィスエリアのクラスタリング」
第十三回10月1日
テーマ
資産運用の対象としての不動産
講師矢口 一成株式会社ゆうちょ銀行 市場部門 常務執行役員不動産投資部長
第十三回目は、矢口一成先生による講義「資産運用の対象としての不動産」が行われました。講義では、組織で経験のない不動産投資を実現するために必要な判断事項として、「資産としての不動産をどう定義するか」「どのような考えでポートフォリオを構築するか」「どう組織を動かすか」という3つの観点について、塾生に、皆さんならどう考えるかを問いかけた上で、矢口先生が実際にどのように判断し、行動したかを説明する形で進められました。その後、不動産投資対象としてのオフィスの今後のあり方や、現状で不動産投資を行うことの合理性について塾生と議論が交わされました。議論では、各自が今後の社会経済の見通しを踏まえ、さまざまな意見が活発に出されました。
【塾生の声】
講師が経験した不動産投資事業立ち上げを追体験する形で議論を行った。その中で不動産を投資対象として定義する過程も興味深かったですが、戦略的思考に留まらず、事業を立ち上げる中で「いかに人(ステークホルダー)に信頼されるか」、そして変化に適応するための「組織構築」の重要性を提言されていたことが印象的でした。AIが容易に答え(と思われるもの)を提供する今この時代にこそ大切にすべきことではないかと考えました。(20代・リネンサプライ業)
ゆうちょ銀行が上場した2015年より高度な運用により収益力強化を図るため、日本政策投資銀行からゆうちょ銀行に参画され、不動産投資事業をスクラッチで立ち上げられた推進力、組織的な意思決定をするためのプロセスに刺激を受けました。また、講義の中で「流動性のない所で不動産を取得し、キャピタルマーケットにアクセスさせる」というキーワードが印象的で、投資家とのリレーション構築のために着実に信頼を積み上げていくこと、先見性を持った情報収集を行い続けることで継続的な不動産投資事業が実現するのだと感じました。(30代・金融業)

2016年にゆうちょ銀行に入行、同行の不動産投資部門を立ち上げ、チームを育成し、約8年間で4兆円を超える不動産ポートフォリオを構築。エクイティ-デット、私募-公募/上場の4象限に加え、地域、物件タイプ、戦略等を軸として計画したグローバル分散投資を実行している。同行入行以前は、株式会社日本政策投資銀行にて都市開発、アセットファイナンス等不動産関連ビジネスに従事。都合20年以上の不動産投融資経験を有する。
ロンドンビジネススクール金融学修士、CFA、CAIA、ARES不動産証券化マスター。
第十二回9月17日
テーマ
場所の意味をほりあてて、形を考える
講師川添 善行建築家(空間構想一級建築士事務所)/ 東京大学准教授(生産技術研究所)
第十二回目は、川添善行先生による講義「場所の意味をほりあてて、形を考える」が行われました。講義では、建築技術が向上に伴い、場所性から建築を考える重要度が減少し、都市が画一化しているという課題や、学問体系の中に歴史が含まれる建築学の特異性が指摘されました。続いて、先生が携わった研究や建築プロジェクトの事例を紹介しながら、建築単体ではなく、場所の特性や人々の行動といったコントロールできない他者性を包含して形にする「建築のカクテル化」という建築論が展開されました。最後は、他者性を包含しながら良い形にまとめる建築の難しさに触れ、それを踏まえた上で次の時代に残るまちづくりを実践してほしいという言葉で締めくくられました。
【塾生の声】
事例と共に示された「建築のカクテル化」という概念が印象的でした。そこにある素材を尊重し、作り手の技術によって新たな価値を創造する。これは、敷地境界線の内側だけで経済合理性を追求する姿勢や、独りよがりな作品主義に陥らずに、場所と人との関係性の中で魅力的な街を創るための実践的な指針だと感じます。不動産に携わる者として、事業計画や収支計算だけでなく、その土地の「意味をほりあて」、未来に誇れる「形を考える」という視座を持ち続けたいです。 (40代・ホテル事業)
意匠設計では奇抜性や作品主義だけではない、街や土地の特性の捉え方が大切で本質的かつ広い面で考えて建築設計すべき、という話は印象的であった。街にシンボリックな建物を作ることは当然悪いことではないが、都市の個性や土地の形状を活かした建築が都市の没個性化を防ぎ、ひいては街の魅力に繋がると理解した。またコントロールできない他者性を包含し、形として統合するという話があったがその考え方こそ、既存の街との共存をめざす上での肝要さであると感じた。 (30代・不動産業)

1979年神奈川県生まれ。東京大学卒業、オランダ留学後、博士号取得。「東京大学総合図書館」、「望洋楼」、「四国村ミウゼアム」、「インド工科大学中央図書館」などの建築作品や、「OVERLAP」(鹿島出版会)、「EXPERIENCE」(鹿島出版会)、「空間にこめられた意思をたどる」(幻冬舎)などの著作がある。
BCS賞、BELCA賞、東京建築賞最優秀賞、日本建築学会作品選集新人賞、グッドデザイン未来づくりデザイン賞、など国内外の受賞多数。
第十一回9月3日
テーマ
人口減少日本の行方 ~世界情勢を見据え、都市と地方はどうなるのか?~
講師内田 要土地総合研究所理事長
第十一回目は、内田要先生による講義「人口減少日本の行方~世界情勢を見据え、都市と地方はどうなるのか?~」が行われました。講義では、まず中長期的な世界経済の動向や、人口減少対策・地方創生といった日本が抱える課題を踏まえ、都市と地方がそれぞれ目指すべき方向性についての説明が行われました。その後、各塾生が関心を持つ日本の課題について意見を述べ合うディスカッションパートに移りました。ディスカッションでは、新たな移動手段としての自動運転技術がもたらす都市構造の変化や、余剰が生じると考えられる公共不動産の活用、地方活性化につながる不動産事業など、個性豊かな考えが共有され、今後のゼミに向けて視野を広げる貴重な時間となりました。
【塾生の声】
内田様から、これまでのさまざまな講義を概観するような大所高所の講義をしていただいたうえで、9期生それぞれから、現時点でゼミのテーマとしたいことについて発言をした。最後に、清水先生より講評があり、全体として非常にインタラクティブな回となった。入塾時から変わらない、自らにとってのキーワードを軸に、考えを再構成するよい機会となった。 (40代・金融業)
今回の講義は、日本の未来を世界情勢と都市・地方の関係から深く考えさせられるものでした。特に人口減少や脱グローバル化の潮流の中、日本の製造業や観光、農業の潜在力、特に地方創生の役割が重要になってくると考えられます。そして東京と地方が「win-win」の関係を築き、デジタル技術で魅力ある地域を創るvisionが大変印象に残り、からくさ不動産みらい塾9期の皆さんと一緒に20~30年先の未来を考える貴重な時間でした。 (30代・総合テベロッパー)

東京大学法学部卒業。建設省入省、国土交通省総合政策局政策課長、大臣官房審議官(不動産担当)、土地・水資源局長、土地建設産業局長を経て、2012年独立行政法人都市再生機構副理事長、2014年より、内閣官房地域活性化統合事務局長、内閣府地方創生室長として、地方創生、国家戦略特区の事務方とりまとめ。2015年11月より不動産協会副理事長・専務理事、2023年7月より現職。麗澤大学客員教授。
第十回-第1部8月20日
テーマ
住宅市場さきよみレポート ~生活者の価値観・心理・不動産の選択~
講師相島 雅樹株式会社リクルート
第1部では、5期生でもあった相島先生による講義「住宅市場さきよみレポート~生活者の価値観・心理・不動産の選択~」が行われました。人口減少や物価上昇、技術進化により従来の供給者優位構造が変化し、生活者が交渉力を持つ存在へと移行していく。そうした中、不動産業を生活者視点で未来志向的に捉え直す必要があるとの説明がありました。具体的には、最近の平屋需要やバルコニー不要化の増加といった事例を紹介し、生活者を“センターピン”として位置付け、変化の兆しを見つけ(シグナル)、流れを読み(パースペクティブ)、俯瞰する(パラダイム)の3つの視点から未来を先読みする事が重要であると語られました。最後は塾生の先輩として、9期生へアドバイス・エールが送られました。
【塾生の声】
将来のことを先読みする際、今まで各種統計やデータをスタートして用いることが多かったが、まずはユーザーや身近な変化の兆しを察知し、フレームワーク化を行うことで思考の整理を行い、その上で各種統計やデータを用いることでより具体的かつユーザーのニーズが反映された先読みが行えるようになるのではないかと感じた。(20代・総合不動産サービス業)
不動産市場のトレンドの変化をミクロから捉えつつ、背景にあるマクロの構造変化を見るというアプローチは体感としてもわかりやすく、未来を予測する上で再現性のあるアプローチだと感じました。また、分析軸を考えるときのひな型としてハイデガーをはじめ哲学を援用する方法論は斬新で、それを踏まえた都市開発のトレンドの変化は、例えば物流など個別のアセットクラスの進化を見るのにもある程度汎用性のある見方だと感じました。 (30代・不動産ファンド)
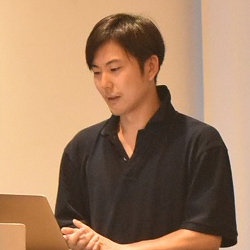
2012年 株式会社リクルートに入社。SUUMOプロダクトの部署に配属。モバイル・AIパラダイムのプロダクト変革に取り組む。2019年 SUUMOリサーチセンターへ配属。主任研究員を経て、2024年より現職。生活者のインサイトに基づく戦略変革に取り組む。慶應義塾大学院メディアデザイン研究科修士修了。訳書に『行動を変えるデザイン』(共訳、オライリー、2020年)『UXデザインの法則』(共訳、オライリー、2021年)
第十回-第2部8月20日
テーマ
消費者行動の変化と小売業のありかた
講師藤原 真
ザイマックス 常務執行役員 / 総合不動産サービス開発事業部担当
ザイマックスコモンズプロ 代表取締役社長
講師山田 賢一ザイマックス総研 主任研究員
第2部では、藤原真さん、山田賢一さんによる講義「消費者行動の変化と小売業のありかた」が行われました。講義はまず、小売業界の市場規模や出店面積の推移、法規制の変遷、最近の商業施設を取り巻く環境の変化についての説明から始まりました。続いて、少子高齢化や商業施設の強みといったキーワードを基に、塾生を交えた今後の 商業施設のあり方についての議論が行われました。議論の中では、”商業施設の機能の複合化が進む”や"モノではなく、サービスや広告といった無形商材を販売する場所になる”など、多様な意見が出ました。最後は、「商業施設は社会の変化を映す鏡であるため、その変化に注目する視点を持ってほしい」という言葉で締めくくられました。
【塾生の声】
時代に応じ、不動産に対するニーズがどのように変化してきたのか、具体的にイメージが沸く形でご講義をいただいた。バブル期にできた店舗用不動産が住居目的でリノベーションされた事例の紹介や、今後も、物流や自動運転、広告など、様々な分野とのビジネスマッチングを引き起こし、新たな価値を生むことが出来る不動産の可能性について、様々な角度から学ぶことができ、新鮮に感じた。 (20代・公務員)
講義の前半では、小売業界の変遷やコロナ禍の影響、環境の変化について解説いただきました。立地の観点で言うと、近年はターミナル駅前での出店が減少し、住宅地域での出店が増加している傾向にあると知り、意外性を覚えました。後半では「これからの小売業・商業施設のありかた」についてディスカッションしましたが、塾生からの売り場自体をメディアにするといった話が印象的でした。様々な環境変化を予測しながら、仮説を立てることの重要性をあらためて感じました。 (30代・不動産投資業)

1998年株式会社パルコ入社。2006年ザイマックス入社後、大型商業施設開発・リニューアル等を数多く牽引、現在は小売企業を中心とした不動産サービス法人営業部門を管掌。京都大学文学部卒業。

1991年大手流通企業に入社。10年以上にわたり、新規出店・改装のプランニング業務に携わる。2007年にザイマックスグループ入社。主に商業施設の運営管理業務を行う。2014年よりザイマックス総研にて商業施設・小売業界の調査研究を担当。上智大学文学部卒業。
第九回8月6日
テーマ
偶発性をデザインする ~人口5000人の徳島県神山町はなぜ進化し続けるのか~
講師大南 信也認定NPO法人グリーンバレー 前理事長
第九回目は、大南信也先生による講義「『偶発性をデザインする 』~人口5000人の徳島県神山町はなぜ進化し続けるのか~」が行われました。講義では、戦前に米国から日本の小学校へ贈られた「青い目の人形」を1991年に里帰りさせた国際交流活動をきっかけに、特定の職種を「逆指名」して移住者を呼び込むワーク・イン・レジデンスなど数多くのプロジェクトを段階的に展開しながら神山町が発展を遂げてきた経緯が紹介されました。「創造的過疎」の考えの元、失敗を恐れず挑戦を続ける姿勢や地域と外部人材との関係性を育み、2023年に開校した「神山まるごと高専」は全国的にも関心を集めています。大南さんの「できない理由よりできる方法を考える」「まずはやってみる」という言葉は、多くの塾生にとって実践への力強い後押しとなったことでしょう。 昨年は、大南先生のご案内により神山町を訪れる現地ツアーが開催され、参加した1期から8期の塾生にとって、現地の空気を感じながら学びを深める貴重な機会となりました。今回の講義を受け、9期の塾生からも早速、現地視察を計画する声が上がっていました。
【塾生の声】
講義を通じて、「すき」な場所を「すてき」な場所に変えるためには「手(て)」を加える必要があるという言葉が特に印象に残った。神山町がアーティストの力を借りて世界のコミュニティに認知されるまでの過程は、偶発性と人とのつながりの力を感じた。 また、ストーリーから入ると行動が目的に収束してしまうという指摘も印象的で、志の高いメンバーが集まり、できることから行動を重ねることの重要性を深く知ることができた。 (20代・デベロッパー)
今までで一番印象的な講義でした。神山町の実績も素晴らしいのですが、こういった結果となったのは大南さんの情熱があったからこそだと感じました。大南さんとお話すると、やったらえんちゃう!の精神がひしひしと伝わってきて物凄く魅力があり、こういったマインドが町全体で醸成されたからこそ、共感する方々が集まってきたのだろうと感じました。 (30代・不動産業)

1953年徳島県神山町生まれ。米国スタンフォード大学院修了。帰郷後、仲間とともに「住民主導のまちづくり」を実践する中、1996年ころより「国際芸術家村づくり」に着手。全国初となる道路清掃活動「アドプト・プログラム」の実施や、「神山アーティスト・イン・レジデンス」などのアートプロジェクトを相次いで始動。町営施設の指定管理や、町移住交流支援センターの受託運営、ITベンチャー企業のサテライトオフィス誘致など複合的、複層的な地域づくりを推進。2023年4月に開校した「神山まるごと高専」設立に発起人/設立準備財団代表理事として参画。
第八回7月23日
テーマ
ウォーカブルな都市の要素とは?
講師樋野 公宏東京大学大学院工学系研究科 都市工学専攻 准教授
第八回目は、樋野公宏先生による講義「ウォーカブルな都市の要素とは?」が行われました。講義では最初に、運動不足の予防のため、都市環境改善によるゼロ次予防が重要であることや、都市計画と公衆衛生の歴史的変遷が概説されました。次に、都市の歩きやすさを構成する主要な概念である”4D(Density, Design, Diversity, Destination) & 2P(Promotion, Placemaking)”の各要素について、優れた歩行環境を整備した事例の紹介、横浜市における歩行推進事業の研究成果、運動の動機付けを行うきっかけとなる事例などをもとに説明が行われました。最後に、日本の都市は歩行環境において世界で見ても優れているという事例が紹介され、そうした環境を今後も維持していくために、4D & 2Pの要素を踏まえたまちづくりの方向性が提言され、講義は締めくくられました。
【塾生の声】
街としての“賑わい・魅力”のような観点での講義を想像していたが、“健康”に着目した切り口だったことに新鮮さを感じた。交通や施設の充実した都市部は、比較的ウォーカビリティを維持しやすいが、ベッドタウンのような郊外部においては人口の高齢化が進むにつれて課題が大きくなってくることを学んだ。抜本的な街づくりのやり直しは現実的でないとすると、講義の中でも触れられたpromotionのようなソフト施策が、より重要になってくるのだろう。(30代・不動産業)
人々の健康が個人の生活習慣だけでなく、まちづくりといった環境要因にも左右されるという視点が印象的でした。都市の密度や土地利用だけでなく、「回遊性」や「プレイスメイキング」など、人が自然に街に関わりたくなる仕掛けの重要性にも共感しました。ショッピングモールなどの事例が、人口密度の低い地域でもウォーカブルな空間を実現できるヒントになる点も興味深かったです。今後は、地方や観光地でどうすればウォーカブルな街を作れるか、という視点を自分の関わるプロジェクトにも活かしていきたいと感じました。 (20代・ホテル事業)

2003年東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程修了。博士(工学)。
独立行政法人建築研究所(当時)を経て、2014年から現職。
都市環境の健康影響を研究し、2022年に「身体活動を促すまちづくりデザインガイド」を公表。
第七回-第1部7月9日
テーマ
スポーツ×不動産
講師太田 和彦
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 ライフサイエンス ヘルスケアスポーツビジネスグループ ヴァイスプレジデント
第七回目は、からくさ不動産みらい塾の卒塾生2名による2部構成で、第1部では太田和彦先生による講義「スポーツ×不動産」が行われました。最初に、企業によるスポーツビジネスへの投資の活発化や、スポーツとそれ以外を組み合わせることで新たな事業機会を生み出す考え方についての説明がされました。続いて、「スポーツ×不動産」のビジネスとして、スポーツに不動産を掛け合わせることによるスポーツチームとしての収益拡大の事例や、日本のスポーツビジネスにはさらなる発展のポテンシャルがあることが示されました。最後は、スポーツエンターテインメントが進化する中で不動産が中心的な役割を担うことを楽しみにしているというエールで講義が締めくくられました。
【塾生の声】
スポーツは新規顧客の獲得とともに地域住民との関係性が重要視されるため、各地でベニュー建設が行われることは納得感がありますが、実際に成功事例を見てスポーツと不動産の密接な関係性を感じることができました。一方で戦況によってはベニュー強化への投資よりもチーム強化に投資すべきではという既存顧客からの声もあるため、「満員のスタジアム」をどう作り上げていくかはバランスが難しいとも感じました。(30代・不動産業)
今回の講義では、不動産業とスポーツのバックグラウンドを持つ講師により、その結節点とでもいうべき、昨今のスポーツビジネスの進化とそれとシナジーを持つベニュービジネスについてご講義頂きました。スタジアムは、長い歴史を持つ不動産ですが、スポーツビジネスの進化により、これまでとは違った形で価値を生み出していることを知り、不動産の更なる可能性に気づくことができました。特に、「満員であることの価値」という視点が新鮮であり、個々のアセットが生み出す価値の本質を突き詰めて考えることの重要さを学びました。(40代・法律事務所)

住友不動産で再開発・住宅営業・人事・海外事業 (台北・上海) 等に従事した後、英・戦略コンサルティングファームL.E.K.コンサルティングを経て現職。サッカー・バスケットボール・ラグビー等を中心としたスポーツビジネスおよびライフサイエンス・ヘルスケアのM&Aアドバイザリー、経営計画策定支援、市場調査支援等を中心に従事。コーネル大学経営学修士。からくさ不動産みらい塾2期生。
第七回-第2部7月9日
テーマ
建設業界の未来
講師原 哲朗
株式会社竹中工務店 開発営業部門 グループ長
第2部では、原哲朗先生による講義「建設業界の未来」が行われました。講義では、最初に建設業がGDPの大きな割合を占める主要産業であることや、業界における喫緊の課題である人手不足やコスト管理の背景要因について説明がありました。続いて、人手不足への対策として給与制度の見直しやロボットの活用による生産性向上の事例が紹介されました。また、建設コスト上昇の中でも事業の採算を確保するため、サステナビリティといった付加価値やエリアマネジメントによる建築物や地域の価値向上の取り組みも紹介されました。最後は、今後のゼネコンは単に建物を建てるだけでなく、建築物の新たな価値を創造する役割が重要になるという考えが、事例とともに示され、講義が締めくくられました。
【塾生の声】
からくさ不動産みらい塾OBで今まさに現場で活躍されている生の声を聞けた臨場感のある講義でした。社会のステージが変わっていくなかで、建設業界が抱えている人手不足等による建築費高騰という課題は非常に本質的で難易度が高いように思いました。一方で、そういった課題に対し、様々な新しい取り組み(建てることではなく、エリアマネジメント、リノベーションによる価値創造等)をされていることを知れたのは大変勉強になりました。(40代・デベロッパー)
日常業務において大きな壁となる「建築費高騰」について様々な角度から実態を学ぶことができた。特に人手不足問題については少子高齢化が止まらない日本において最善の解決策がなにかは、未来を見据えて考え続けていきたい。働き方改革の緩和や職種に対するイメージ改革、DX化、外国人受入れなど策は多岐に渡るだろうが根本となる「建築業界の仕組み」自体を変えていく必要があるのではと感じた。また、一方で建築費が高騰したとしても必要な収益が得られれば問題がないのでは、とも感じたため都心でも地方でも成立する効率の良い収益モデルについても考えていきたい。(30代・小売業)

2000年 株式会社竹中工務店 入社
開発営業部門に所属し、公有地や開発案件を担当。2010年に大手不動産会社へ出向等を経て、2015年に現在の開発営業部門に所属。からくさ不動産みらい塾1期生
第六回6月25日
テーマ
先を読むためのアナロジー思考~VUCA時代の不連続な発想法~
講師細谷 功ビジネスコンサルタント・著述家
第六回目は、細谷功先生による講義「先を読むためのアナロジー思考~VUCA時代の不連続な発想法~」が行われました。講義では、変化が激しくAIの進化も著しい中、経験から考えるだけでなく、一見関係が薄そうな事象の中から抽象的な共通点を見出し、課題解決に活かす”アナロジー思考”の重要性について説明がありました。加えて、「自分の仕事が何に似ているかを考え、どのような点で似ているのかを説明する」や「時間の小分け化というキーワードで進化したサービスが何かを考える」など、異なる事象の共通点を考えるワークを通し、アナロジー思考の実践が行われました。ワークを通して、塾生からは普段の業務ではいかに近い世界の中だけで物事を考えているか実感したなどの声が上がりました。
【塾生の声】
手元ばかり見ていると見えないことも、抽象化することで俯瞰でき、新たな発見ができるため、未来を読み解くためにとても重要な能力だと思った。すぐに身につくものではないが、意識で変えることのできる思考なので、今後実践していきたいと思った。また講義中、「アナロジー思考」についてAIに問う場面があったが、AIは当方の考え方をすでに習得しており、脅威を感じるとともに、未来を生きる上でAIを使いこなす必要性についても改めて感じた。(30代・金融業)
「一般的な模範解答のようなもの」はすぐにAIが作ってくれる時代において、特に「より本質的かつ具体的な問題発見」と「創造的・越境的な思考」をするための思考法を具体例も交えながら学べました。また、越境的な思考をするためには、レコメンドされた情報で埋め尽くされる中、敢えてアンテナを立てて遠い世界に興味を持つことが重要だと感じました。 (20代・リネンサプライ業)
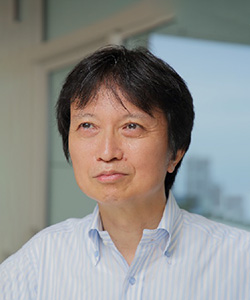
神奈川県生まれ。株式会社東芝を経て、アーンスト&ヤング、キャップジェミニ、クニエ等の外資系/日系のグローバル・コンサルティングファームにて業務改革等のコンサルティングに従事した後独立。近年は問題解決や思考力に関する講演やセミナーを企業や各種団体、大学等に対して国内外で実施。著書に『アナロジー思考』(東洋経済新報社)、『具体と抽象』(dZERO)、『具体⇔抽象トレーニング』(PHPビジネス新書)などがある。
第五回6月11日
テーマ
不動産市場における10年の構造変化~変化をいかにビジネスチャンスにするか~
講師榎本 英二野村不動産ホールディングス株式会社 参与
第五回目は、榎本先生による講義「不動産市場における10年の構造変化 ~変化をいかにビジネスチャンスにするか~」が行われました。講義では、最初にビジネスを考える上で将来の構造変化を見据えて「仮説」を持つことが重要であるとの話から始まりました。次に、「時代の終わりの始まり、不都合な真実が現実に?」をテーマに、「新築からセカンダリー(既存)」「世界の運用資産“2京円”の世界に向けて」「人生100年時代」「グリーン投資、新エネルギー、そしてAI/データセンターの世界へ」など9つ項目について解説を行った後、ご自身の仮説を述べられました。最後に、塾生一人ひとりが考える仮説に対して、榎本さんがコメントを添えて講義が終わりました。
【塾生の声】
今回の講義で「不動産は、流動性がある限りはマーケットの中で上がり下がりがあってもどうにかなる」というお話がありました。日頃の業務においてはどうしても近視眼的な出口戦略に陥りがちなこともありますが、不動産投資・開発は長いタームで行われる事業であり、マクロ経済、技術革新、世界情勢、人々のマインドの変化等様々な要因を踏まえて自分なりに仮説を立てたうえで考えていく必要があると強く感じました。(30代・デベロッパー)
今回講義を要約すると「10年後の未来に自身の仮説をもって事業に取り組む」になるが、多角的な視野・知見を持ち、時には大胆かつ無謀とも思われるポジティブな仮説をもつことで初めてビジネス機会が見い出せると感じた。企業に所属する中で仮説に基づく事業立案をすることは容易ではないが、企業・個人として変革が求められる今の時代だからこそ、このマインドを忘れずにチャレンジングなビジョンを持ち続けるべきと感じた講義であった。講義終盤の塾生が考える未来の仮説発表も様々な視点があり、興味深い内容であった。(30代・不動産業)

1985年慶應義塾大学経済学部卒業。1985年野村不動産入社、経理・総合企画・商品開発・資産運用事業に携わる。2008年執行役員 資産運用カンパニー副カンパニー長兼運用企画部長、2009年野村不動産投資顧問副社長、2013年野村不動産常務執行役員法人営業本部副本部長、2015年野村不動産アーバンネット専務執行役員を経て2017年同代表取締役兼副社長執行役員就任、2021年 野村不動産ソリューションズ(旧 野村不動産アーバンネット) 代表取締役副社長、2024年 野村不動産ホールディングス 執行役員(DX推進統括)を経て、2025年4月より現職の野村不動産ホールディングス株式会社 参与。
1990年大手米国年金基金との米国不動産投資を開始し、1997年からは日本の不動産投資に着手、2001年不動産私募ファンド運用のため、野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社設立。2002年には日本の運用会社による初めてのオポチュニティファンドである日本不動産オポチュニティ・ファンド(JOFI)の組成・運用を手がける。2004年以降、同社の安定型不動産私募ファンド(Smileシリーズ)の組成に携わり、2005年野村不動産投資顧問株式会社を設立、不動産証券化商品への投資に着手。2010年私募REIT第一号を運用開始。2013年野村不動産にてCREを中心とした法人営業を担当。2015年野村不動産アーバンネットにて仲介・CRE部門の企画を担当。(2021年4月1日より「野村不動産ソリューションズ」に社名変更)、同社のデジタルマーケティング、DX戦略を推進。2024年野村不動産ホールディングスにて、グループ全体のDX戦略推進を担当。
宅地建物取引主任者、日本証券アナリスト協会検定会員
第四回5月28日
テーマ
ラグジュアリービジネスのいま
講師金山 明煥
東急株式会社 執行役員
講師セオドア・言・ニフィング
Plus Curiosity 創業者・代表取締役
第四回目は、金山明煥先生、セオドア・言・ニフィング先生による講義「ラグジュアリービジネスのいま」が行われました。講義では、まずラグジュアリーのキーワードとして、論理ではなく感情に訴える付加価値や、いまここでしかできない体験といった視点が示されました。次に、現在ラグジュアリーの領域は「モノ」「体験」「ライフスタイル」の3つに分けられ、ラグジュアリーブランドの戦略は、より後者の領域へとシフトしていることが説明されました。併せて、顧客層の若年化・多様化や、フィジカルな空間で体験を提供する上での不動産の重要性についても触れられました。講義の最後は、都市開発にラグジュアリーをどのように取り入れるかについて、実際の開発事例を交えた説明で締めくくられました。
【塾生の声】
「マスへの迎合は価格競争を引き起こし、経営効率を下げることにも繋がる」という言葉が印象的でした。ビジネスとして取組む以上は規模の議論が不可欠で、マスを優先する思考に偏りがちです。しかしながら「ラグジュアリー」に求められる希少性は、マスの対極にあるとも言えます。ビジネスにおいて、希少性と普遍性のバランスを取っていく為に、どのように取り組んでいく事ができるのか。難しい話ですが、だからこそ、うまくはまれば得られる果実も大きいのだと思いました。(40代・ホテル事業)
ラグジュアリーとは何だろうか。これ迄は、サラリーマンマインドからIRR等の投資指標にとらわれ、アートや文化等効果が見えにくい価値について思い切って考えたことはなかった。講義の中で「日本は1泊5万円のホテル“は”クオリティが高い」という話があったが、インバウンド消費、特にアッパー層のニーズを掴むためには、これまでのマインドを改める必要があると強く感じた。一方で、日本の資源を活かすことで彼らにとっての真のラグジュアリー「一生に一度きりの特別な体験」を提供する余地は十分にあるとも感じたので、数字で測れない世界観にも向き合っていきたい。(30代・金融業)

東急株式会社 ホテル・リゾート事業部 執行役員。早稲田大学(建築学専攻)卒業後、東急建設株式会社に入社。その後、マサチューセッツ工科大学に留学し修士課程(都市計画およびマネジメント)修了。帰国後、東京急行電鉄株式会社(現、東急株式会社(以下、「東急」)に転籍し、東京大学博士号(都市計画)取得。東急では、組織再編、リテール事業、不動産事業、およびホテル事業など多岐事業に従事し、株式会社東急ビッグウィーク(タイムシェアリゾート事業)および株式会社THM(新宿2ホテルオーナー事業)の代表取締役社長を歴任して現職に至る。また、留学中よりULI(Urban Land Institute)に所属し、日本におけるULI設立時の創設メンバー。

2018年に東京でプラス・キュリオシティを立ち上げる以前は、香港を拠点にCushman & WakefieldのAPAC地域リテール部門責任者を務めた後、アジア・中東のショッピングセンター・デベロッパーへのアドバイスやプレイスメーキングに特化したコンサルタント会社であるHusband Retail ConsultingのCOOを歴任した。また、上海に5年間駐在し、Appleの地域リテール拡大担当を経て、Cushman & Wakefieldの中国リテールリース事業の責任者として貢献した。セオは東京出身の日米ハーフである。
第三回-第1部5月14日
テーマ
働き方×ワークプレイス
ザイマックス総研のリサーチから
講師石崎 真弓
ザイマックス総研 主任研究員
第三回目は、2名の講師による2部構成で、第1部では石崎真弓さんによる講義「働き方×ワークプレイス ザイマックス総研のリサーチから」が行われました。講義は、最初に塾生に向けて今どのような働き方をしているか、その働き方に満足しているかの問いかけから始まりました。その後、ザイマックス総研が公開した働き方に関するレポートをもとに、コロナ禍前後のワークプレイスや働き方の変化の説明や、現在のオフィスの課題と見られる点や今後のワークプレイス戦略についての考察が示されました。最後は、最近の工夫されたワークプレイスの事例や、グローバルな視点での東京の競争力についての説明が行われ、講義が締めくくられました。
【塾生の声】
時間軸を長く取ると、いつからか誕生した間接部門が拡大、人を集めるために出現したオフィスについては、近年まで「人数」が最大のボトルネックであった。そこから、ITの進展により、この「人数」の制約が緩和されたことで、自由度が高まり、オフィスがあたかもソフトのようになってきたことは興味深い。講義を受けて、塾生自らもオフィスのスタディツアーを企画、論理と実践を通じて深い理解につなげることを予定している。この「実践」も可能な本塾の良さを存分に享受し、さまざまなテーマにおいて、一歩でも二歩でも手触り感のある学びを積み上げていきたい。 (40代・金融業)
「講義を通して、オフィスとして従来のようにただ床を貸し出すだけでなく、生産性向上やコミュニケーションの活性化、従業員のモチベーション向上等に寄与するオフィスの重要性が益々高まってきていることを痛感しました。コロナ禍を経てリモートワークをはじめとした多様な働き方が広がる中、より付加価値の高い、ワーカーに選ばれる場所を提供することで、社会全体での生産性向上に寄与できればと、不動産業界にいる一員として思いました。 (30代・不動産投資業)

リクルート入社後、リクルートビルマネジメント(RBM)にてオフィスビルの運営管理や海外投資家物件のPM などに従事。2000年RBMがザイマックスとして独立後、現在のザイマックス総研に至るまで一貫してオフィスマーケットの調査分析、研究に従事。近年は、働き方と働く場のテーマに関する調査研究、情報発信している。日本ファシリティマネジメント協会、オフィス学会、テレワーク協会、テレワーク学会また日本サステナブル建築協会知的生産性研究コンソーシアムに研究参加。
第三回-第2部5月14日
テーマ
技術・社会の未来予測と建築不動産産業へのインパクト
講師河瀬 誠
立命館大学(MBA)教授 / MK&Associates 代表
第2部では、河瀬誠先生による講義「技術・社会の未来予測と建築不動産産業へのインパクト」が行われました。講義では、デジタル技術の急速な進化により、多くの「新常態」が常識へと転換しつつあり、20年後には現在では考えられないことが当たり前になる可能性が示唆されました。続いて、デジタル技術の進化とともに建設業のロボット化や人口動態、世代間の価値観の変化、シェアエコノミーといった産業・生活両面での変化が起こっていることが紹介されました。最後は、都市の主役を車から人へという視点に基づいた、従来の常識とは異なる新たなまちづくりの事例が提示され、「未来の妄想から出発して、今後の都市を考えてほしい」という言葉で締めくくられました。
【塾生の声】
今回の講義を通じて、デジタル技術の進化が社会・都市・生活に与える影響を改めて実感した。特に、ムーアの法則に基づく加速度的な技術の進歩が今後業界の破壊をもたらすという内容は大きな衝撃であった。環境の変化に対応した組織作りと、本質的な価値を磨き続ける努力の重要性を学ぶ良い機会となり、視座を高く持つことの必要性を再認識した。 (20代・総合デベロッパー)
デジタル/テクノロジーがいかに我々の社会や生活を変えているかについて学び、その指数関数的な変化のスピードを踏まえると、今の常識を前提に未来を考えることは適切ではないという点を痛感しました。また、社会のニーズや価値観の多様化を踏まえ、ビジネスが提供するプロダクトは、今後いかにニッチな点を攻めていけるかが重要、という点も講義の中で印象的なポイントでした。大きい組織、会社であればあるほどマスにアプローチする必要がある一方で、金太郎飴的な再開発ビルが集客等に苦戦しているような事例を見ると、不動産業界にとっても当てはまる重要なポイントではないかと感じました。 (30代・不動産ファンド)

東京大学工学部計数工学科卒業。ボストン大学経営大学院理学修士および経営学修士(MBA)修了。A.T.カーニー、ソフトバンク、ICMGを経て、現職。著書に『知的資本経営入門』(生産性出版)、『未来創造戦略ワークブック』『経営戦略ワークブック』『戦略思考コンプリートブック』『新事業開発スタートブック』『海外戦略ワークブック』(以上、日本実業出版社)『戦略思考のすすめ』(講談社現代新書)『マンガでやさしくわかる問題解決』『課題解決のレシピ』(日本能率協会)などがある。
第二回4月16日
テーマ
不動産市場の未来:未来の不動産市場のリスク
講師清水 千弘一橋大学教授・麗澤大学副機構長学長補佐
第二回目は、当塾のアドバイザーでもある清水千弘先生による講義「不動産市場の未来:未来の不動産市場のリスク」が行われました。講義は、2017年に予測された、未来のアメリカの不動産市場のレポートに基づき、当時の予測が実際に正しかったのか、また日本ではどうであったのかを軸に、予測された要素に関連する研究を紹介する形で進められました。研究事例としては、人口減少と都市への集中による日本の人口分布の変化、人口減少・高齢化・国際化が不動産価格に与える影響、不動産バブル崩壊のプロセスなどの研究が取り上げられました。講義の最後は、「30年後のリスクを予想し、それをコントロールして未来を作る議論をしてほしい」という言葉で締めくくられました。
【塾生の声】
清水先生の講義を通して様々な観点から不動産の未来を予測可能であることを学んだが、近年、建築物の老朽化対策、空き家問題等のリスクに着目しがちであり、人の感情や、技術革新の動向に着目した政策がなかなか進んでいないように思う。今後、限られたリソースで未来について考えていくには、リスクを全て解消しながら進んでいくのか、割り切って進むのか、岐路に立たされているため、未来のビジョンを強く掲げ続けることに必要な判断力を磨くにあたり、自分自身学び続けていきたいと感じた。(20代・公務員)
不動産業界の構造的課題や、人口動態・地域衰退といった大きな社会的テーマと不動産の関係性について深く考える機会をいただきました。普段の実務では得られない理論的な視点や、先進的なデータ活用の事例にも触れることができ、非常に刺激的な時間となりました。(30代・総合デベロッパー)

一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科教授、麗澤大学学長補佐 国際総合研究機構長、清華大学不動産金融センター顧問。東京大学博士(環境学)。プリティッシュ・コロンビア大学、シンガポール国立大学、香港大学 客員教授、マサチューセッツ工科大学Research Affiliate、麗澤大学経済学部教授、日本大学教授、東京大学特任教授を経て現職。専門は、指数理論・ビッグデータ解析・不動産経済学。主な著者に、『Property Price Index』Springer(共著)(2020)、『日本の物価・資産価格』東京大学出版会(渡辺努氏と共編(2023))など多数。Member of CRE。
第一回4月9日
テーマ
開講式・不動産の見方、考え方
講師中山 善夫ザイマックス総研 代表取締役社長
からくさ不動産みらい塾第九期がスタートしました。今期は様々な業種から20名の塾生の参加となりました。最初に開講式が行われ、中山塾頭から、からくさ不動産みらい塾の設立からリニューアルまでの背景・経緯や、これまでの塾生達の様子などを伝え、塾生達への期待を述べる挨拶が行われました。その後、中山塾頭による第一回目の講義「不動産の見方・考え方」が行われました。講義では、最初に不動産とは何か?という話がされ、続いて時代に応じて不動産の使われ方が変化する中、世の中と不動産のこれからを考える上で重要な視点についての説明が行われました。講義の最後は「飛耳長目」を大事に、1年間を頑張ってほしいという塾生たちへのエールが送られ、第1回目講義が終了しました。
【塾生の声】
第一回の講義では、不動産はお金儲けの手段ではなく、大切な資源であり、国そのものであることなど、不動産の本質的な価値について、多くの気づきを得ました。 普段の業務ではどうしても収益性に注目しがちですが、もっと高い視座で不動産を見て、どう「みらい」を作っていくべきなのか、塾の仲間たちとこの1年間議論できることにワクワクしています。(30代・不動産業)
創設の背景、中山塾頭の熱い思いを伺う中で、不動産に何らかの形で携わっているこの志高いメンバーと1年間、様々なことを学び不動産業界に何らかのインパクトを与えられるように奮闘したいという思いが強まった。1回目の講義を受講して、不動産が関係しない業界はないので、不動産以外の分野の知見を深めることで一層不動産への理解が深まるのではないかと感じた。(20代・総合不動産サービス業)

株式会社ザイマックス総研代表取締役社長。ニューヨーク大学大学院不動産修士課程修了。一般財団法人日本不動産研究所で数多くの不動産鑑定・コンサルティングに従事。その後、ドイツ証券にてドイツ銀行グループの日本における不動産審査の責任者を務める。2012年よりザイマックスグループの役員に就任、現在、ザイマックス総研にて不動産全般に係る調査研究を担当。不動産鑑定士、MAI、CCIM、Fellow of RICS、Member of CRE。ARESマスター「不動産投資分析」科目責任者、不動産証券化協会教育・資格制度委員会委員。